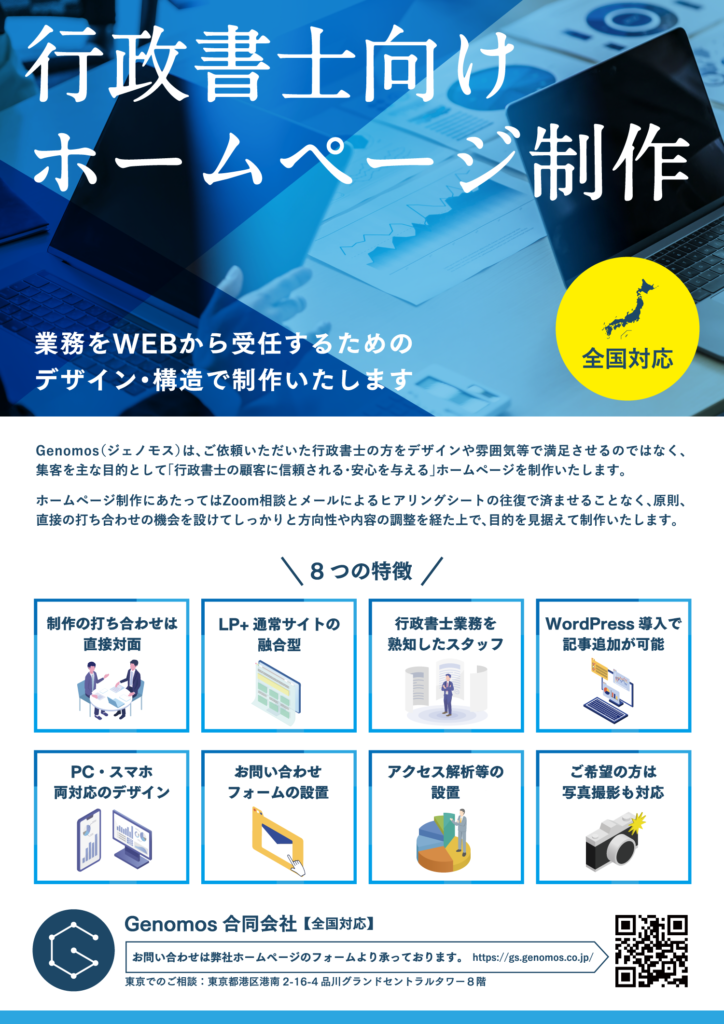これまでのウェブサイト集客は、専門知識という商品を一つひとつ丁寧に棚に並べ、記事などで事務所の魅力を伝え、お客様が安心して入れるような店構えをコツコツと整えていく作業に似ていました。その誠実な店作りが、やがてお客様からの信頼と、問い合わせという形での「ご来店」につながっていたという構造でした。
ところが、ChatGPTやGeminiといった生成AIの登場は、お客様のお店の探し方や、商品の選び方そのものを大きく変えてしまう可能性を秘めています。
例えるなら、お客様一人ひとりに非常に優秀なコンシェルジュがついて、最適な答え(行政書士事務所)を直接案内してくれるようなものです。お客様は、わざわざ色々なホームページ(お店)を一つひとつ見て回らなくても、そのコンシェルジュの説明だけで満足してしまうかもしれません。
そんな生成AIの存在によって「自分のウェブサイトが、素通りされてしまうようになるのではないか?」 「これまでの地道な情報発信は、意味がなくなってしまうのだろうか?」「いまからホームページの記事追加を頑張る意味はあるのだろうか」 「そもそも、なんだか難しくてよくわからない」という不安が生じるのは当然のことです。
そこで今回のコラムでは、生成AIの登場によって、行政書士のウェブサイト集客が今後どう変わっていくのか考察してみたいと思います。
AIの登場で、私たちのコンテンツ作りはどう変わっていく?
生成AIがもたらす影響は、ユーザー側の変化だけではありません。実は、私たち行政書士自身のコンテンツ作りにおいても、AIは心強い味方になってくれる可能性があるのです。
ここからは少し視点を変えて、まず制作者側の視点で、日々のコンテンツ作りがどのように変わるのかを見ていきたいと思います。
先ほど、生成AIを「優秀なコンシェルジュ」に例えましたが、もう少し身近な存在で言うと、「非常に賢く、文章を書くのが得意な新人アシスタント」と考えてみると分かりやすいかもしれません。
この新しいアシスタントは、行政書士が依頼すれば、事務所の業務内容を紹介する文章のたたき台を瞬時に作ってくれたり、難しい法律用語をユーザー向けに分かりやすく言い換える案をいくつも出してくれたりします。これまで記事の作成に何時間もかかっていた人にとっては、業務の負担を大きく減らしてくれる心強い味方になる可能性があります。
しかし、その一方で、少し注意が必要な側面もあります。
例えば、このアシスタントが書く文章は、とても流暢でわかりやすいのですが、どこか機械的で、先生ご自身の経験からくる言葉の重みや、お客様を想う温かみが伝わりにくいことがあるのです。また、先ほどの「コンシェルジュ」の話のように、多くのお客様がAIの提供する便利な答えだけで満足してしまい、先生のホームページにたどり着く前に疑問を解決してしまう、という場面も増えてくるでしょう。
つまり、AIの登場によって私たちのコンテンツ作りは、「楽になる部分」と「これまで以上に注意や工夫が必要になる部分」の両方が生まれる、ということです。
では、具体的にどのような作業はAIに任せやすくなり、逆に、私たち人間がこれまで以上に心を込めて行うべきことは何なのでしょうか。
AI時代のコンテンツ作りのポイント
AIという、まるで「賢いアシスタント」のような存在が登場したことで、私たちのコンテンツ作りの考え方も少しずつ見直しが必要になってきました。
これは、車の運転に少し似ているかもしれません。目的地まで最短ルートを教えてくれる便利なカーナビ(AI)が登場しても、実際にハンドルを握って安全に運転し、目的地を決めるのは、やはり私たち自身です。
AIに任せやすい作業、得意なこと
それでは早速、「賢いアシスタント」であるAIに、どのようなお仕事をお願いできるのかを見てみましょう。行政書士がこれまで時間をかけて行ってきた作業の多くを、AIは手伝ってくれる可能性があります。
例えば、以下のような作業です。
- 記事の構成案(目次)作り: 「〇〇手続きについてブログを書きたい」と伝えると、読者が知りたいであろう項目をいくつか提案してくれます。
- 専門用語の分かりやすい言い換え: 難しい法律の言葉を、中学生にも分かるような平易な表現に書き直してくれます。
- タイトル案をたくさん出してもらう: ホームページのコラム記事で、人の目を引くようなタイトル案を10個ほど考えてもらう、といったことも可能です。
- SNSの投稿文作成: ブログの更新をお知らせするX(旧Twitter)やFacebookの投稿文を、手軽に作成してくれます。
このように、AIはコンテンツ作りの「たたき台」や「下書き」を用意するのに非常に長けています。
ただし、一つだけ大切な注意点があります。それは、AIが作った文章をそのまま公開しないことです。
AIは「それらしい」文章を作るのが非常に上手いため、一見すると正しい情報に見えても、しれっと間違った情報(ハルシネーション)を紛れ込ませることがあります。行政書士が誤った情報を発信するのは命取りになりかねません。
AIはあくまでアシスタントですので、必ず行政書士自身の専門知識で内容を厳しくチェックし、言葉を修正することが、自分とお客様の信頼を守る上で不可欠なステップです。
AIには書けない、人間にしかできないこと
AIが作成した文章は、とても滑らかで分かりやすい反面、どうしても「誰が書いても同じ」ような、平均的な内容になりがちです。ですが、自分自身で書いた文章にはその人それぞれの文体やリズム感が現れますし、個人個人の経験や実績についてはAIには書けません。
- 具体的な経験談: 「以前、このような状況でお困りだったお客様が、この手続きを通じて安心された様子を見て、私も嬉しくなりました」といったエピソードは、AIには書けません。
- 行政書士独自の視点や意見: ある法律や制度について、どう考え、実務家として何を感じているかということもAIには書けません。
- 事務所の理念やお客様への想い: なぜこの仕事をしているのか、どのような想いで日々お客様と接しているのかといった個人的な心情もAIには書けません。
AIが作れるのは、誰でも調べられる範囲のことであり、もっとも「それらしい」だけの文章です。しかし、行政書士自身の経験や実績を元に語る文章はAIに書けません。
E-E-A-T(信頼性)がますます重要になる理由
AIによって、世の中に情報が溢れれば溢れるほど、お客様は「一体どの情報が本当に正しいのだろう?」と、ますます慎重になります。そこで重要になるのが、「E-E-A-T」という考え方です。
これは、Googleがホームページの品質を評価する上で非常に大切にしている基準で、特に専門性の高い情報を扱う行政書士にとっては、以前から重要でした。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
AIは、もっともらしい文章をいくらでも作れてしまうからこそ、これからのウェブサイトでは、「この記事は、〇〇の業務を専門とし、豊富な実務経験を持つ、実在する行政書士の〇〇が、責任を持って書いています」ということを、これまで以上に明確に示す必要があります。
具体的には、詳細なプロフィールページの作成、顔写真の掲載、監修者情報の明記、実際の経験に基づいた事例の紹介などが挙げられます。こうした一つひとつの情報が、AIには作れない「信頼の証」となるのです。
小手先のテクニックに走るのではなく、行政書士が持つ専門性や誠実な人柄をホームページ上で丁寧に表現することが大切になってきます。
記事作りにおいても、一方的な情報提供にならないよう、語りかけるような口調を取り入れるなど、ホームページ上で一定の信頼を得られるような工夫がより重要になってきそうです。
専門的な知識を公開した先にあるもの
ここまでは、AIには書けない「専門家らしさ」や、専門家としての「信頼性」をホームページで表現することが、これまで以上に大切になる、という考察をしてきました。
しかし、ここで一つ、気がかりな問題が出てきます。 それは、「せっかく苦労して書いた専門的な記事が、お客様の目に直接触れる前に、AIに要約されてしまうかもしれない」という可能性です。まるで、丹精込めて作った商品の説明書きを、お店に来る前にお客様専属のコンシェルジュが読み上げてしまい、お客様はそれで満足してお店には立ち寄らない、といった状況に似ています。
行政書士の場合は専門的な知識や経験といった無形のものを提供して対価を受け取ることも多いため、説明書きどころか、核心的な知見自体をAIが提供することになってしまうおそれすらあります。
「サイトに来てもらえないかも?」ゼロクリック検索との向き合い方
行政書士がホームページを運営する上で、アクセス数の増減は気になる指標の一つだと思います。しかし、AIの登場によって、このアクセス数の考え方自体を少し変える必要が出てくるかもしれません。そのキーワードが「ゼロクリック検索」です。
これは、ユーザーがGoogleなどで何かを調べた際に、AIがそのページ上で直接答えを教えてくれる現象のことです。そのため、ユーザーはわざわざホームページのリンクをクリックすることなく疑問が解決し、満足してしまう、というわけです。
この影響で、これまで専門的な記事などで集めていたホームページへのアクセス数は、全体的に少しずつ減少していく可能性があります。
しかし、現時点では、これを過度に恐れる必要はないと考えています。
なぜなら、複雑なご相談や、実際に業務を依頼しようと真剣に考えているお客様は、AIが示す表面的な答えだけでは満足しないからです。そうしたお客様は、「どんな先生なのだろう」「本当に信頼できる事務所だろうか」と、より詳しい情報や先生の人柄を知るために、必ずホームページを訪れてくれます。
むしろ、これからは「AIの回答の引用元になる」ことを目指す、という新しい視点も生まれます。AIは様々な情報源を元に回答を作りますから、ホームページが「信頼できる情報源」としてAIに認められれば、AIの回答に「行政書士〇〇事務所のサイトを参考にしています」といった形で表示されるかもしれません。これは、事務所の権威性を高める、新しい形でのアピールになるとも言えるでしょう。
そのためこれからは、単なるアクセス数に一喜一憂するのではなく、いかに「信頼できる情報の発信源」として、お客様やAIに認識されるかが重要になってきそうです。
知識や経験、そして「つながり」が重要になる
では、AIにも認められ、お客様からも「直接この事務所に相談したい」と思ってもらえるようになるためには、具体的に何が必要なのでしょうか。現時点では以下の3つが大切になると考えています。
一つ目は、「より深い専門知識」です。AIが答えるような一般的な知識の一歩、二歩先を行く、ニッチで専門的な情報や、行政書士自身の足で集めたような独自のデータは、AIには決して真似のできない貴重な価値を持ちます。
二つ目は、「顔の見える経験談」です。お客様の具体的なお悩みや、それを解決した先の未来を語るストーリーは、いつの時代も人の心を動かす最強のコンテンツです。
そして三つ目が、お客様との直接的な「つながり」です。
これからの時代、ホームページで情報を一方的に発信するだけでなく、SNSやメールマガジン、あるいは小規模なセミナーなどを通じて、お客様や見込み客の方々と直接コミュニケーションを取る機会を作ることが、重要になってくるかもしれません。
これからは、ホームページを単なる「情報発信の場」としてだけでなく、「お客様とつながるための拠点」へと、少しずつ進化させていくような意識が必要かもしれません。
もし、この3つのうち「まだあまり取り組めていないな」と感じるものがあれば、まずは一つ、ご自身の事務所でできそうなことから試してみてはいかがでしょうか。
どこまで見せる?大切な情報の「公開範囲」を考えるヒント
さて、これまではホームページで「何を」発信していくか、というお話を中心にしてきました。ここからは少し視点を変えて、「そもそも、大切な情報をどこまで公開するのか」という、さらに一歩踏み込んだテーマについて考えてみたいと思います。
これから生成AIが進歩していく過程で、「行政書士自身が公開した専門的な知見をAIが学習した結果として、AIだけで問題が解決できてしまうようになってしまう」という状況にもなりかねません。
こういった将来に向けて、何を考えておけばいいのでしょうか。
「非公開」という選択肢を用意しておくべきかもしれません
これまで、ウェブサイトでの集客は「有益な情報は、できるだけ広く公開しましょう」というのが基本的な考え方でした。しかし、AIがあらゆる公開情報を学習する時代にあっては、「あえてすべてを公開しない」という選択肢も、これからは視野に入れる必要が出てくるかもしれません。
もちろん今すぐにという話ではありませんが、将来的に採りうるひとつの選択肢として考えておいてもいいのではないでしょうか。
この選択には、いくつかのメリットが考えられます。
- 情報の希少価値を高める: 「この詳しい話は、〇〇先生に直接相談しないと聞けない」という状況は、先生の専門家としての価値やブランドイメージを、かえって高める効果があります。
- 直接的な収益につなげる: 非常に専門的なノウハウを、有料のセミナーや個別相談、あるいは会員制のサービスでのみ提供することで、情報そのものを収益の柱にできる可能性があります。
- AIによる安易な利用を防ぐ: 先生が長年の経験で培ってきた、独自のノウハウや貴重な情報を、AIに無償で学習されることを防ぐことができます。
しかしその一方で、この「非公開」という選択肢は、とても慎重に判断する必要があります。
一番の懸念は、「新しいお客様に見つけてもらえなくなる」リスクです。
お店のシャッターを固く閉ざしてしまえば、外からはどんなに素晴らしい商品が中にあるのか、うかがい知ることはできません。有益な情報を無料で公開することは、行政書士の存在や専門性を広く知ってもらい、信頼を得るための大切な第一歩でもあるのです。
「非公開」という戦略は、事務所の価値を守るための強力な一手になり得ますが、同時に、新しい出会いの機会を減らしてしまう可能性も秘めた、いわば諸刃の剣とも言えます。事務所が今どのような状況で、今後どのような方向を目指すのかによって、その判断は大きく変わってくるでしょう。
こんな状況になったら公開範囲を見直すタイミングかも
では、具体的にどのような状況になったら、この「情報の公開範囲」を見直すことを検討し始めるべきなのでしょうか。もちろん、すべての事務所に当てはまる絶対の正解はありませんが、いくつか参考になる「サイン」のようなものはあります。
- サイン① 市場の変化: 周囲の行政書士事務所が、相次いで有料のセミナーや会員制のサービスに力を入れ始めたとき。
- サイン② ウェブサイトの変化: ホームページのアクセス数はそれなりにあるのに、具体的な問い合わせやご相談に繋がる割合が、目に見えて減ってきたとき。
- サイン③ AIの変化: 行政書士が発信する専門的な情報と、AIが生成する情報の「質の差」がほとんど無くなってきた、と感じたとき。
- サイン④ ビジネスの変化: 無料での情報発信に多大な時間と労力をかけている一方で、そこから得られる成果(集客や評判など)とのバランスが、どうにも合わないと感じ始めたとき。
もし、これらのサインに複数当てはまるようであれば、そのときが情報の公開方針について考えてみるタイミングかもしれません。
もちろん、いきなり全ての情報を非公開にする必要はないとは思いますので、「最新の法改正に関する詳しい解説は、メールマガジンの読者様限定で」「具体的な申請ノウハウは、有料セミナーでのみお話しする」といったように、情報の種類によって段階的に公開レベルを変えてみるということになるでしょうか。
おわりに
ここまで、生成AIの登場によるホームページ集客の変化と、その向き合い方について、様々な角度からお話ししてきました。
非常に賢いアシスタント(AI)が現れたことで、私たちのコンテンツ作りは、これからもっと楽になっていくかもしれません。しかしその一方で、そのアシスタントが優秀すぎるあまり、お客様がお店(ホームページ)まで足を運んでくれなくなるかもしれない、という新しい課題も生まれています。
だからこそ、お店の看板である「信頼性(E-E-A-T)」を丁寧に磨き上げ、店主である行政書士自身にしか語れない商品のストーリー、つまり「ご自身の経験や想い」を大切にすることが、これまで以上に重要になりそうです。そして時には、どの商品をショーウィンドウに飾り、どの商品を特別な応接室でお見せするか、という「情報の公開範囲」を、戦略的に考える視点も必要になってくるかもしれません。
ですが、これまでの地道な取り組みが決して無駄になるわけではありません。むしろ、行政書士として目の前の仕事を誠実に行い、専門知識と経験を積み上げてきたその「土台」があればこそ、AI時代の変化に対応できるのです。
大切なのは、その土台の上に、この記事でお話ししたような新しい視点(AIの賢い活用、人間ならではの価値の追求、お客様とのつながりの構築)を少しずつ取り入れ、ウェブサイトを時代に合わせて進化させていくことだと思います。
今後の生成AIの進化によっては様々な対応が必要になってくるかもしれませんので、そういった動向にアンテナを張っていくことは大切ですが、過度に振り回されすぎないように上手にAIと付き合っていくことが重要ではないでしょうか。